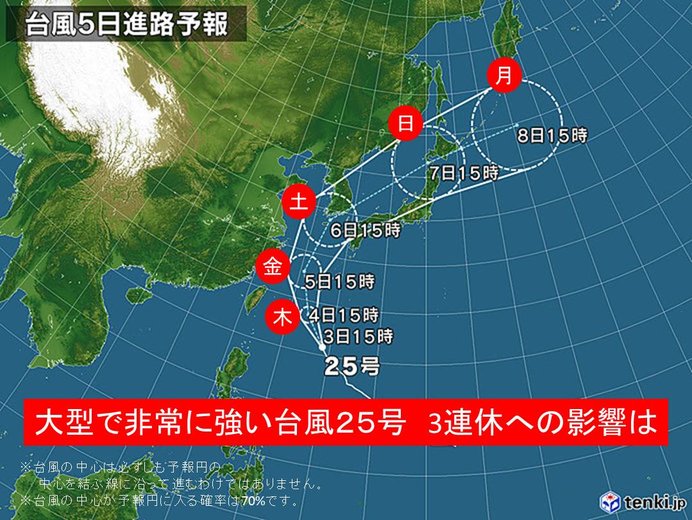今日は「宇宙の日」、「国際宇宙年であった1992年に、日本の科学技術庁(現・文部科学省)と宇宙科学研究所(現・宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 JAXA)が制定した記念日」(Wikipedia)とのこと。
ソ連のスプートニク衛星、ガガーリンの地球周回、初の女性有人宇宙飛行士のテレシコワ、アメリカの弾道飛行したシェパード、グリソム(いかにも軍人らしい風貌が格好よかった)が蘇ってくる。そして月面着陸のアームストロング船長。
子どもの関心とともに宇宙開発の歴史が進んだ。子どもたちを後押ししたのがテレビのSFドラマだ。今のSF映画は奇想天外な物語が多いが、子ども時代に見た米国のテレビドラマ「宇宙探検」は、科学的であり、異星人(宇宙怪物)と遭遇するといった物語りを繰り広げる以前のものだった。
(本ブログ関連:”テレビと宇宙”)
(以前の本ブログで触れたことがあるが)昔、家庭用テレビが珍しかった時代、近所の家に集まって白黒のブラウン管テレビを見せてもらっていた。まるで映画を楽しむようにアメリカの番組を楽しんだ*。「ハイウエイパトロール」のダン・マシューズ隊長、「宇宙探検(Men into Space)」のエドワード・マコーリー大佐の思い出が今も残る。そしてテレビは瞬く間に普及し、「潜水王マイク・ネルソン(SEA HUNT)」や「裸の町(The naked city)」など、いずれもしっかりした大人の主人公が登場した。
(*)民放テレビは、映画館の入場料を払わず、タダで漫画「ヘッケルとジャッケル」を見せてくれた。
(本ブログ関連:”マイクネルソン”)
NHKアーカイブスに「宇宙探検」(放送年度 1959~1960年度)が記されている。
https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009040888_00000
---------------------------------------------------------------
当時、最新の科学知識に基づいて未来の宇宙征服の夢を描いた空想科学シリーズ。国防省はじめ各宇宙開発研究団体の協力でロケット打ち上げの実写をふんだんに使い、精巧な特殊撮影と共に迫力を生んだ。主人公のマコーレー大佐は常に冷静沈着で、どんな事故にも対処する勇気と能力を持ったスーパーマン。同時に人間的な温かさも兼ね備え、ドラマとしての厚みを出した。(白黒/吹替/アメリカ/原題: Men Into Space)
音楽:ヴィクター・ヤング**
---------------------------------------------------------------
(**)ヴィクター・ヤング
上記解説に「音楽:ヴィクター・ヤング」の名があるが本当だろうか。
彼の、映画「エデンの東」、「八十日間世界一周」の名曲を知らぬ人はいないだろう。「黒い牡牛」も忘れられない。多分、初めてレコード店に一人で行って買ったEPレコードだったと思う。